自転車の交通ルールを知らずに走るのは非常識だし危険
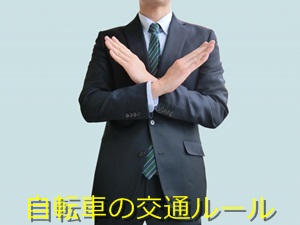 道路交通法では
道路交通法では
第13節 自転車の交通方法の特例
(自転車道の通行区分)
第63条の3 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第121条第1項第5号)
以下63条の10まで有ります。
が定められて居ます。
施行規則では
第2章の2 自転車に関する基準
(普通自転車の大きさ等)
第9条の2 法第63条の3 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190センチメートル
ロ 幅 60センチメートル
(2) 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 1の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
(制動装置)
第9条の3 法第63条の9第1項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前車輪及び後車輪を制動すること。
(2) 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
(反射器材)
第9条の4 法第63条の9第2項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第32条第1項
の基準に適合する前照燈(第9条の17において『前照燈』という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
の様に定められて居ます。
自転車は本来、「軽車両」に属する乗り物なので、原則として歩道では走ってはいけませんが、日本の事情・経緯がある中で、この様などっちでも走って良いよと言う変な法律になってしまったのです。
自転車はあくまでも車道を走るのが原則で、歩道の走行は禁止されています。
しかし特例として自転車通行可の標識がある場合はその歩道を走っても良いことになります。
つまり自転車通行可の標識がない歩道は、自転車が走ることはできません。
自転車通行可の標識がある歩道を走る場合は、右側でも左側でもかまいませんが歩道の車道側(車が走っている側)を走らなければなりません。
そしてスピードも徐行(時速10キロぐらいのいつでも停止できる速度)しなければなりません。
実際は自転車は歩道を走ることが黙認されています。
日本には自転車専用レーンが殆どないですし、車道の路肩には必ず路肩駐車している車がいます。
よって車道だけを走行することを自転車走行者全員に強いるのは、現実的ではありません。
但し、車道走行における際と同じように歩道でも「左側通行」をして頂きたいものです。
速度違反
自動車と同じ速度が制限です。その道路の標識の速度です。
自転車でそんな速度が簡単に出せるとお思いでしょうか?
自転車で自動車より速く走るつもりなのでしょうか?
事実上、ロードレーサーあたりしか、速度制限に掛かる自転車はいません。
で、そのような自転車は、ほとんどの人が自分でメーターを付けてます。
子供
保護者に監督責任があります。
自転車を公道で乗らせるのなら、保護者に交通ルールを教える責任があります。
当然、信号は守らなくてはなりませんが、車道走行時は基本的には車道の信号に従います。
時々難しいのは『車道の左車線が左折専用レーンになっているのに、自転車は直進したい場合』ですが、この場合でも、自転車は左車線からの直進が認められています。
ただ、後ろから追い抜きざまに左折してくるクルマとの巻き込み事故というのも多発しており、用心は必要です。
ロードバイクに乗っている人などは、それを防ぐ為に、事前に左車線の中の右に寄って、そこから直進する人もいます。
2車線以上ある交差点での一発右折は禁止です。
 スポーツバイク・自転車乗りの総合情報
スポーツバイク・自転車乗りの総合情報