脳神経が筋肉を支配しているので脳を上手にコントロールしよう!
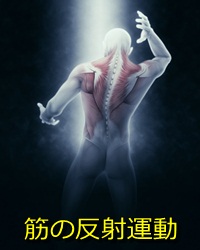 神経の筋制御
神経の筋制御
私たちのからだの運動は、神経系によってたくみに制御されています。じっさいに動くのは、骨格筋の収縮‐伸長による骨です。神経系の中枢は脳で、とくに意識は大脳のはたらきによります。したがって、私たちが手足を動かそうと意識すると、大脳からの電気信号が神経軸索を通じて脊髄にとどきます。
そこで、信号はシナプスをへて運動神経に伝達され、筋肉に伝えられます。そのさい、脊髄でのシナプスには二種類あります。 一つは運動神経の末端にある終板のように、興奮をそのまま伝達する「興奮性シナプス」です。もう一つは、興奮を止めてしまう「抑制性シナプス」です。これはマイナス電荷の塩素イオンを細胞膜から汲み入れて、活動電位を消滅させるのです。
そのため、脳からの信号を脊髄で二つに仕分け、拮抗筋の一つは筋収縮を起こさせ、他は伸長させることができるわけです。
どのように神経が筋肉を支配しているのかは、たいへん複雑ですが、もっとも単純な反射運動からみていきましょう。
反射
私たちは、熱い物にさわると無意識に手をひっこめます。釘をふみつければ、あわてて足をひっこめます。皮膚の感覚細胞が熱いとか痛いとか感じると同時に手足が動きます。これは、私たちが大脳で熱いと認識して、それから手足をひっこめようと動かすのではありません。このように、脳が関与しない、つまり無意識で起こる反応のことを「反射」といいます。
一番簡単な「屈曲反射」では、次のようなしくみで起こります。熱い物にふれると、皮膚の温度感覚受容器から感覚神経を通じてインパルスが脊髄に伝えられます。感覚神経軸索は二つに分かれて、 一本は興奮性シナプスを通じて運動神経をへて屈筋を刺激し、収縮させます。もう一方は抑制シナプスに接しているので、インパルスは仲筋にいたる運動神経を興奮させず、したがって伸筋は伸びたままです。これらの結果、腕を曲げることになります。
皮膚からの信号は、脊髄から別経路で大脳に伝達され、熱いと知覚します。そのときには、すでに手はひっこみかけているわけです。
椅子に座ってひざの下をかるくたたくと、 一瞬足がポンと上がります。この反射は膝蓋腱反射とよばれ、よくお医者さんがからだの状態を調べる検査に使われます。ひざをたたくと、大腿四頭筋というひざを伸ばす筋肉が収縮します。筋繊維中にある「筋紡錘」といわれる収縮‐仲長をキャッチできる感覚器官が″ひざたたき″を感覚して、感覚神経を興奮させ、インパルスを脊髄に伝達します。そして、興奮シナプスを通じて大腿四頭筋を収縮させます。他方、対になっている大腿二頭筋は、抑制性シナプスによってインパルスが伝えられないので伸長したままです。そこで、足が一瞬だけ上げられることになります。
私たちの運動には、動かそうという意思によって起こす動きと、そのような意思に関係なく生じる動きとがあります。同じ筋の収縮でも、関節を伸ばそうという意思で生じる動きと、ある特定の刺激により、脳からの指令がないまま生じる動きがあります。
後者の代表が「反射」です。よく知られているものに、膝蓋腱反射があります。膝蓋骨の下方にある膝蓋腱をたたくと膝関節が伸展するのは、腱がたたかれることによって膝書謙菫に)菫結する大腿茜韻訪が瞬間的に伸ばされ、その結果、大腿四頭筋に収縮しようとする働きが起こったためです。
この反射は、腱や筋線維の伸びを感じ取った情報が、末梢神経を介して脊髄に伝えられ、脊髄で筋線維を収縮させる指令が出ることで起こります。刺激は脳まで行かず、脊髄で戻ってくるため、非常に短時間で動きが起こります。熱いものや冷たいものに触れたとき、瞬間的に指を引っこめる動作が起こるのも反射と同じです。
意思による運動
動かそうという意思に基づく動きは、大脳の一次運動野の特定の部位に対応する神経細胞(一次運動ニューロン)が刺激されることで起こります。神経細胞の突起は脊髄を下降しますが、途中で交差して大部分は脊髄の反対側に行き、ここを伝わった刺激が二次運動ニューロンを刺激します。
二次運動ニューロンは、神経根や末梢神経の中で運動繊維となり、筋肉で各筋線維に枝を伸ばしています。そこに刺激が伝えられることで、筋収縮を引き起こすのです。この経路を錐体路と呼びます。
末梢神経の働き
末梢神経は、神経根から伸びる神経線維(正確には神経細胞の軸索突起)の束です。
頚部や腰部では、複数の神経根が合流したり分岐したりする神経叢を作り、やがて末梢に至ります。神経の中を刺激が伝わる速さは、毎秒50~70mという速さです。生後半年から1年ほどで、成人と同じくらいの速度になっています。
運動神経を伝わった刺激は、その先端にある特殊な構造である神経筋接合部に行きつきます。刺激が伝わってくると、その先端からアセチルコリンという神経伝達物質を放出します。この物質が筋肉側にある受容体に結合すると、筋肉の収縮が開始されるのです。一方、皮膚では、温度や圧力などのさまざまな情報が、それぞれの受容体によって受け取られます。この刺激は、末梢神経の中の知覚神経の線維を伝わって上行します。
脊髄に到達する直前にある神経節を経て、脊髄内で二次ニューロンとなり、上行して大脳に情報が伝達されます。末梢神経は支配する領域が決まっているため、どの末梢神経からどのような刺激が伝えられたかによって、体のどの部位でどんな刺激が加わったのか感知されます。
神経細胞は軸索突起という非常に長い突起を持っています。この突起が束になり、目に見える太さの神経を構成しています。
神経の損傷には、内部の軸索突起のみの損傷から、神経の束を取り囲む周膜という膜も含めて完全に切れる損傷まであります。神経が強い圧迫を受けた場合には、軸索突起の損傷が起こり、軸索突起内の流れが途絶することがあります。
途絶した部位から末梢寄りの軸索突起が壊死することもあります。さらに、軸索が切れてしまう損傷や、周囲組織や周膜まで損傷されるものもあります。
たとえば、肘の内側の尺骨神経を打撲して手の小指側がしびれても、数分で回復するのは、手枕をして眠ったために、手関節や指が伸展できなくなり、回復まで1カ月以上かかることがあります。
損傷は、多くの場合、軸索が自然に回復したり、再生したりして治ります。軸索の再生速度は中枢側ほど速く、末梢では遅くなります。たとえば、肩や肘では1日に5mm程度の速度で再生しますが、手関節では1~ 2mmです。
また、軸索が伸びるための道すじも損傷しているので、これが離れていると軸索の再生は起こりません。その場合、神経腫という神経のこぶを作ってしまい、痛みやしびれがあります。したがって、神経の周囲の膜を縫い合わせる手術が必要になります。
 スポーツバイク・自転車乗りの総合情報
スポーツバイク・自転車乗りの総合情報