からだのメカニズムを理解するため3つのことを意識して運動をしよう
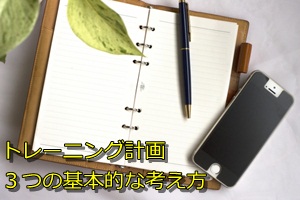 筋力トレーニングの考え方を理解したらいよいよトレーニング計画を立てます。現実にはジムのインストラクターやスタッフに相談して決めることになりますが、ここでは、頭に入れておくべき3つの基本的な考え方をお話しします。
筋力トレーニングの考え方を理解したらいよいよトレーニング計画を立てます。現実にはジムのインストラクターやスタッフに相談して決めることになりますが、ここでは、頭に入れておくべき3つの基本的な考え方をお話しします。
① ピリオダイゼーション
生物は環境が変わるとその変化に適応していく、という生物学的な基本原理があります。これはトレーニングにも当てはまります。2~3ヵ月同じトレーニングを続けていくと、身体がそれに適応して、わかりやすく表現すると「慣れて」しまいます。こうした適応は、トレーニング効果を頭打ちにさせてしまいます。
そのため、筋力トレーニングを年間通じて同じ内容でするのではなく、月別・季節ごとなど、強弱のリズムをつけて行うことが理想的だ、というものです。これを「ピリオダイゼーション」とよびます。ただ、この概念はある程度レベルの高い中・上級者向けです。初心者の場合は、トレーニングに強弱をつける前の、基本的な筋力アップが必要です。長い期間の一本調子トレーニングは少々覚悟してください。
②大きな筋群から小さな筋群へ
ジムでのトレーニングで、全身の筋力増強を目的とした場合の、典型的なトレーニング種目とその順序例を示しました。一般的に、体幹に近い大きな筋肉群から小さな筋肉群へ向かってトレーニングをするほうが、安定した全身の筋力増強につながります。
ほかにも、一番必要としている筋群のための種目から優先的に行うとぃう「プライオリティ・プリンシプル」というトレーニング手法もあります。初心者であれば大きな筋肉群のうち、まず筋力アップが必要な筋肉はどこか、を見極めてこの手法を利用します。たとえば腰周りが弱いので腹部を強化しなければいけない、という場合は腹部、腰背部の筋トレーニングを一番初めに行う、これは、この手法にのっとった筋力トレーニングです。
③スプリットルーチーン
トレーニングを続けていくと、トレーニングボリュームも上昇しますし、超回復メカニズムの考慮も難しくなります。そういう方は、「トレーニングの細分化」をお勧めします。身体の部位別にコース分けし、実施するコースを日によって変えてトレーニングしていくという方法です。
「スプリットルーチーン」といいます。
たとえば、週3度のトレーニングをするとします。そこをA、B、C、の3つのコースに分け、Aでは大胸筋や広背筋を中心に、Bでは肩・上腕筋群を中心に、Cでは下半身の筋群をトレーニングします。一日のトレーニング時間を短縮することができますし、内容も濃くなります。
反対に、心臓の機能や血管の伸縮性・弾力性などが衰えると、心筋梗塞や脳血管疾患という病気が待っています。ここでは心肺機能と運動との関係をみてみます。
ジムでウォーキングやランニング運動をすると、心臓はどう変化するのでしょう? まず、酸素運搬経路をたどりながら運動と心肺機能との関連をみてみます。
全身運動に必要なエネルギーを生み出すために、心臓はあらゆる組織で酸素を供給します。
①呼吸によって肺に酸素が取り込まれ
②肺胞の毛細血管で拡散、酸素が血液中へ溶け込み
③酸素を含んだ血液が肺静脈を経て心臓へ
④心臓から全身へ血液が繰り出され
⑤各組織(筋肉や他の組織・器官)で酸素が順次取り込まれる
このような流れで、運動中、心臓から繰り出された血液は、体中を素早く駆け巡ります。心臓へ戻り、また心臓から繰り出される、このメカニズムがスムーズに展開されることで運動も成立するのです。また、運動強度が高くなるにつれ、呼吸数も同時に増えるため、酸素摂取量も同様に増え、酸素運搬能力が高くなります。
ジムで全身運動をする際、心拍数(1分間に心臓が鼓動する拍動数)がひとつの指標として用いられます。これは手軽に運動強度を設定でき、自分の体力レベルに合わせて全身運動を展開することが可能となるからです。
軽い運動をした場合、最初は息が切れますが、そのうちに身体が慣れてくるものです。いっぽう、全力疾走のような激しい運動は長く続けることができません。これは、軽い運動の場合は、運動開始直後に心拍数の急上昇が見られますが、その後はやや低下し、ほぼ定常を保つのに対し、激しい運動では、開始直後に心拍数が急上昇し、その後も上昇傾向を維持するためです。その結果、やがて運動継続が不可能になるのです。このように運動で心拍数が変化することを心拍数応答といいます。
ただし、どんなに心拍数が上昇しても220を超えることはありません。身体がたとえ応答可能でも脳のほうが危険と判断してブロックをかけます。
 スポーツバイク・自転車乗りの総合情報
スポーツバイク・自転車乗りの総合情報